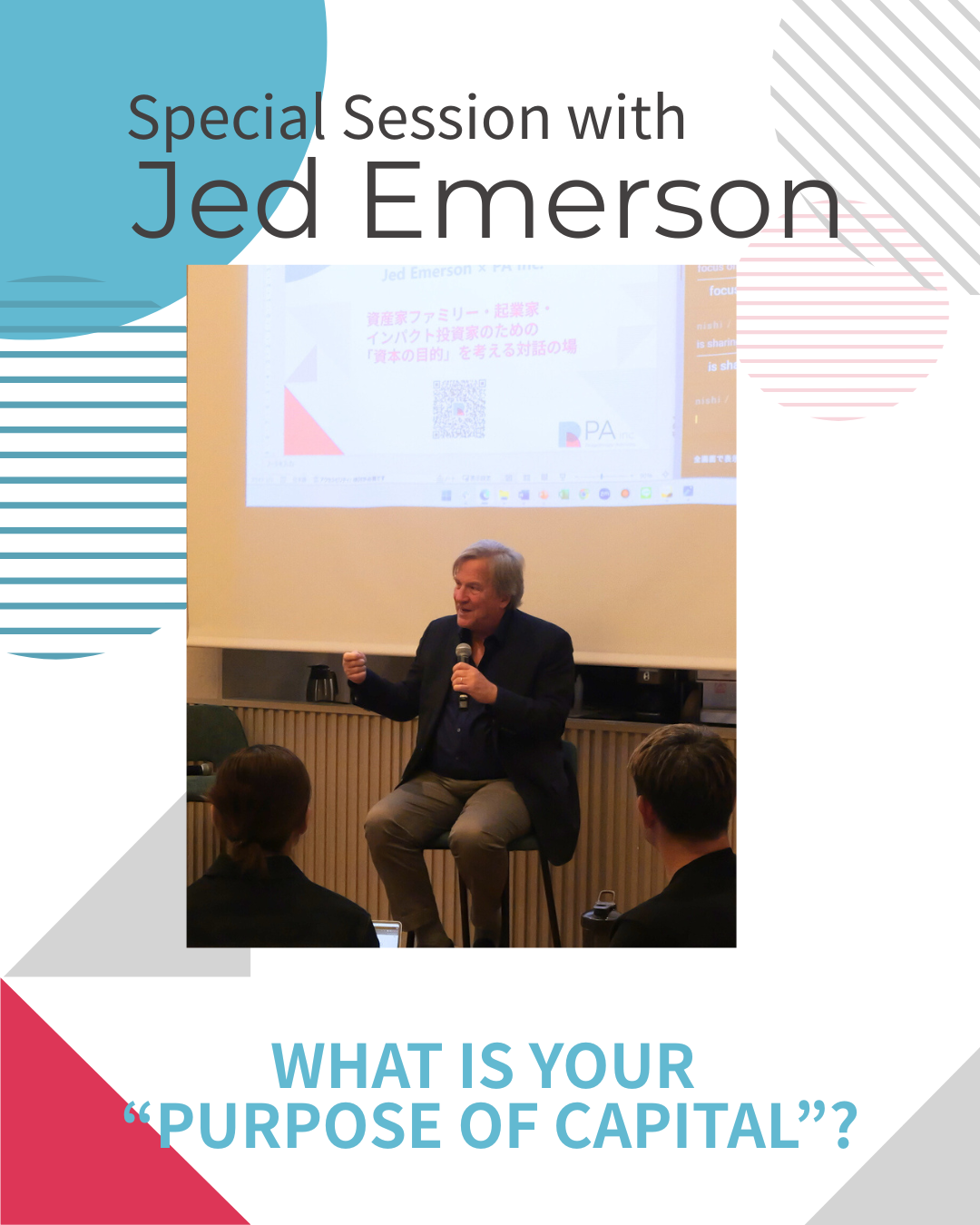KNOWLEDGE
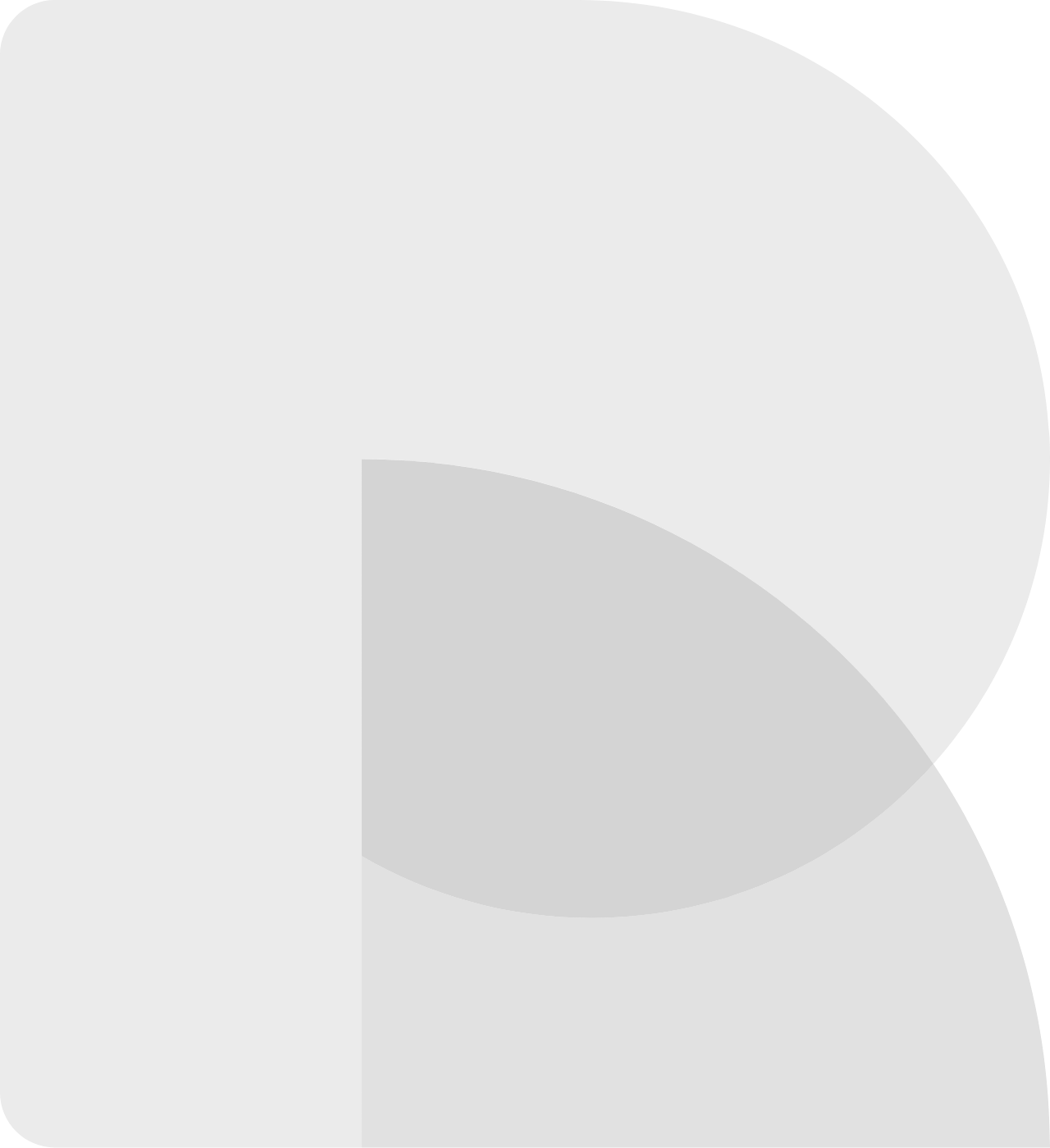
福留大士さん 社会課題解決の糸口は“型化”。起業家視点をフィランソロピーにシフトして見出した独自の道

プロフィール
福留 大士(ふくどめ ひろし)
株式会社 チェンジホールディングス(東証PRM3962) 代表取締役1976年鹿児島県生まれ。アンダーセンコンサルティング(現アクセンチュア)を経て、2003年に株式会社チェンジを設立。現在は株式会社チェンジホールディングス代表取締役兼執行役員社長を務める。また、SBI地方創生サービシーズ株式会社の代表取締役社長や、複数のグループ企業等で取締役や社外取締役を兼任し、地方創生やスタートアップ支援に積極的に取り組んでいる。
社会貢献(=フィランソロピー)については、災害支援、2018年にM&Aしたトラストバンクにおけるふるさと納税の普及、政策起業家支援プロジェクト「Policy Fund」のアドバイザーなどで活躍。単なる寄付にとどまらず、政策提言や地方創生、寄付文化の醸成など、幅広い手法で フィロンソロピ―活動を行う。まさに、企業経営とフィロンソロピ―両立させたビジネスリーダー。
福留さんは、「地方創生」というビジネスを通じて社会課題の解決に取り組むだけでなく、プライベートでも災害支援や政策提言支援に積極的に関わっています。
このように、社会の様々な課題に自ら果敢に向き合う福留さんの姿勢から、彼のフィランソロピーとは何かを探っていきたいと思います。
福留さんにとってのフィランソロピーとは?
― 起業家としての能力や財力で、NPOやNGOの経営が上手く回るサポートをすること
僕はビジネスも社会課題の解決そのものだと思っています。いわゆる経済合理性を伴うもので、かつ課題も大きい領域はたくさんあります。例えば医療や社会インフラの構築もそうです。つまり、既にお金が動いていて非常に根深い課題がある領域は、ビジネスそのものです。
一方で、課題はあるけどお金がつかない領域もたくさんあります。海洋汚染が進んでいるから、海洋プラスチックを収集しましょうという課題はあるけど、「これって誰がお金出すんだっけ?」とか。みんな解決してくれる “誰か” の登場を待っている。そんな領域が、ビジネスの対極にあるとも思っています。
それらの間に、グレーゾーンもたくさんあります。社会課題の解決を目的としたマーケットが生成できているところと、経済合理性がないが故に誰も手をつけていないが本当はメリットが大きいところ。その間のグレーゾーンを限りなくビジネス寄りにするのが起業家の社会貢献活動だと、僕は思っています。
例えば、NPOやNGOは、善意や寄付で成り立っていますが、なぜこれらがビジネスロジックで動けていないのかと言うと、最たる課題は「バランスシートがないこと」。だから、僕が今一番やりたいのは、この「バランスシートがないこと」をなんとか解決することです。NPO・NGOが、資金を集めて、それを運用して、活動資金を作れるようになること。そうすればNPO・NGOにも活動資金が流入し、そこでさらに生まれた資金を活動に投下できるからインパクトの大きい活動ができるはずです。
そのケース作りとして「特定非営利活動法人ピースウィンズ・ジャパン」や「空飛ぶ捜索医療団ARROWS」へ、僕らがヘリコプターや病院船を提供することで、彼らが災害時の活動に上手く活かせるような支援をしています。
自分の起業家としての能力や財力で、NPOやNGOの経営が上手く回るサポートをするということが、僕の中での社会貢献、フィランソロピーの定義です。
福留さんが挑戦している「地方創生」は課題が大きすぎるように感じますが、どのように取り組んでいかれますか?
― 「くまモン」のように型を作って思いっきり広げていけば、みんなが乗っかってくれるはず

僕が地方創生で1番好きなのは「くまモン」です。「熊本にくまモンがいたから日本全国にゆるキャラが広がりました」という、そのレベルの工夫をみんなでできる環境がとても大事だなと。要は、「くまモン」のような、クリエイティブでなくてもマネができるような、型・フォーマットをつくることが重要だと僕は思っています。
商売って最初は地道な活動ですが、一定値を超えるとすごくレバレッジが効く状態になります。「レバレッジとは何か?」というと、標準化とか型化だと思うので、フィランソロピーの領域にも絶対に型があると僕は思っています。この型を突き止めて、思いっきり広げていくということをやりたいです。地方創生に取り組んでいるとエリアは広いしテーマも複雑で前に進みづらいものばかりですが、型をつくるとみんなそれに乗っかってくれるはずです。
例えば、ふるさと納税サイトの「ふるさとチョイス」というプラットホームをやっているのですが、これをきっかけに楽天やソフトバンクなど、名だたる会社がリソースを投入してふるさと納税をやってくれたので、元々は80億円程度だったマーケットが、10年で、一気に1兆円にまでなりました。
こういうビジネスのロジックは、絶対にフィロンソロピ―にも応用できるはずです。なのでここから先は、ふるさと納税のような型をどれくらい作れるかに、ひたすら挑戦ですね。まだ進捗率1%くらいですけど。型をつくるという意味では、今、サイバーセキュリティ事業で地方のサイバーを守ること、AIやロボットテクノロジーの活用で人手が不足しているところに救済策を講じること、あとは観光インバウンドにおける型づくりなどに、ビジネスとして重点的に取り組んでいます。
フィランソロピーへ、これほど強い関心を持たれるのはなぜですか?
― 良い社会・良い時代をつくって、次世代に引き渡したいと思ったから
僕は歴史が大好きなんですが、歴史を見ても人間の善さが出ると良い時代が続き、愚かさが出ると悪い時代が続くので、僕自身も良い社会・良い時代をつくって次世代に引き渡したいです。それが自分が人として生まれてきたある種の理由ではないかと思っています。
経営者や起業家の方々の中には、フィランソロピーに踏み込むことを躊躇される方も多いように思います。福留さんはどう考えますか?
― フィランソロピーとは行き着くところ、「お前は何者か?」を問うもの

フィランソロピーへの取り組みは「誰々だからできる」とか「ビジネスでの一定の経験が必要」なのではなくて、結局は「何を目指すのか?」や「どうしたいのか?」ということだと思います。いかようにでも、みんな自分が設定したテーマに取り組めると思いますし、そこに何らかのインパクトを残せると思います。なので、自分が目指したいところはどこなのか?自分がどう社会に働きかけたいのか?どんな世界を残したいのか?を突き詰めて考えると、それぞれのテーマに行き着くと思います。
とはいえ、起業家同士で集まるとどうしても経営や政治の話が多くなるので、そういった深い話はよほど仲の良い人とでない限りあまりしないかもしれませんね。
フィランソロピーについてや、人生の目的を考えた上での抽象度の高い話って、結局「お前は何者か?」みたいなことだと思うので。でも、僕の場合はビジネスの話も全部そっちの方向に持っていくので、自然とそういうアジェンダになりがちではあります。
最後に、日本でフィランソロピー活動を行う中で感じる「期待」や「課題感」などがあれば教えてください。
― フィランソロピストの活動の連鎖を広げるために、テーマ・エリア毎のコミュニティの地図がほしい
コミュニティが欲しいなと思います。例えば、「文化芸術の振興をしてるのは〇〇財団の〇〇さんを中心とした、この30人」など、テーマ毎に “これが自分のライフワーク” と定めている人たちのコミュニティです。もしくは、〇〇市はXXさんが支援しているとか、エリア軸のコミュニティでもいいかもしれません。
どうしても、みんなの活動が断片的になっているので、各々がより上位の目的で繋がることができればもっとパワーが出ると思います。
今の現状をみると、みんなが自分たちの能力で、それぞれのコミュニティ内だけで協力を仰いでいる状態なので、エネルギーに全然レバレッジがかかっていないと思います。なので、テーマ・エリア毎のコミュニティが可視化できる地図的なものがあると良いですね。
どこかの団体がフィランソロピー活動の中で得たノウハウは他の団体にもどんどん転用すべきですし、そうやって徐々に良い連鎖が広がっていくといいなと思います。
お話を伺って...
福留さんの取り組みには、起業家として培ったビジネスの視点と、社会課題に対する強い責任感が共存しています。
特に印象的だったのは、課題と資金の間に横たわるギャップを仕組みで埋めようとする姿勢。
支援や善意に頼るだけではなく、持続可能な方法で社会インパクトを広げていく発想は、今後のフィランソロピーの実践に新たな視座を与えてくれます。
「個人の力で何ができるのか」を超えて、「どんな仕組みをつくれば、多くの人が巻き込まれるのか」を問い続ける福留さんの姿は、これからの社会変革において欠かせないロールモデルの一つと言えるでしょう。
インタビュアー:Co-CEO 藤田淑子
TOP