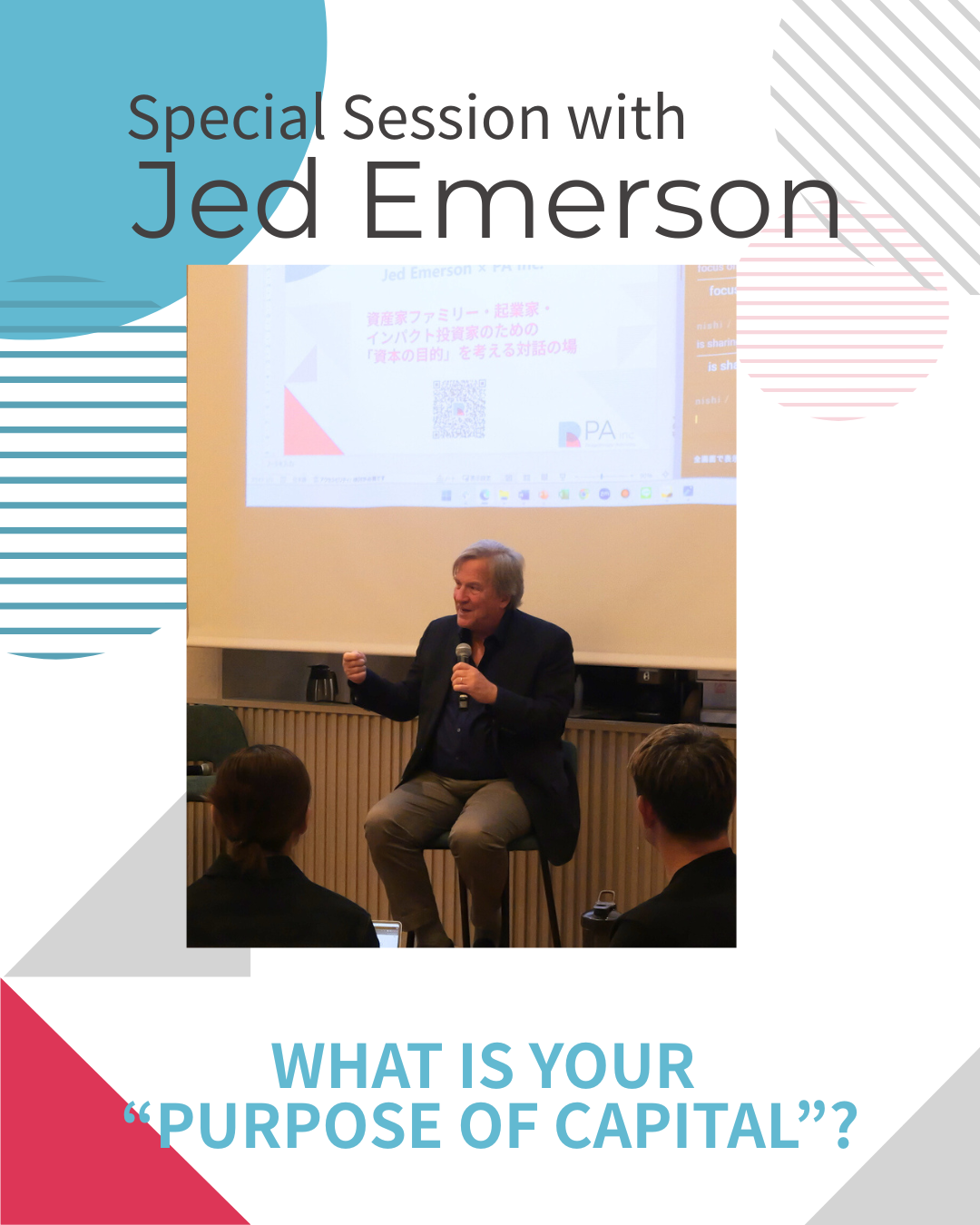KNOWLEDGE
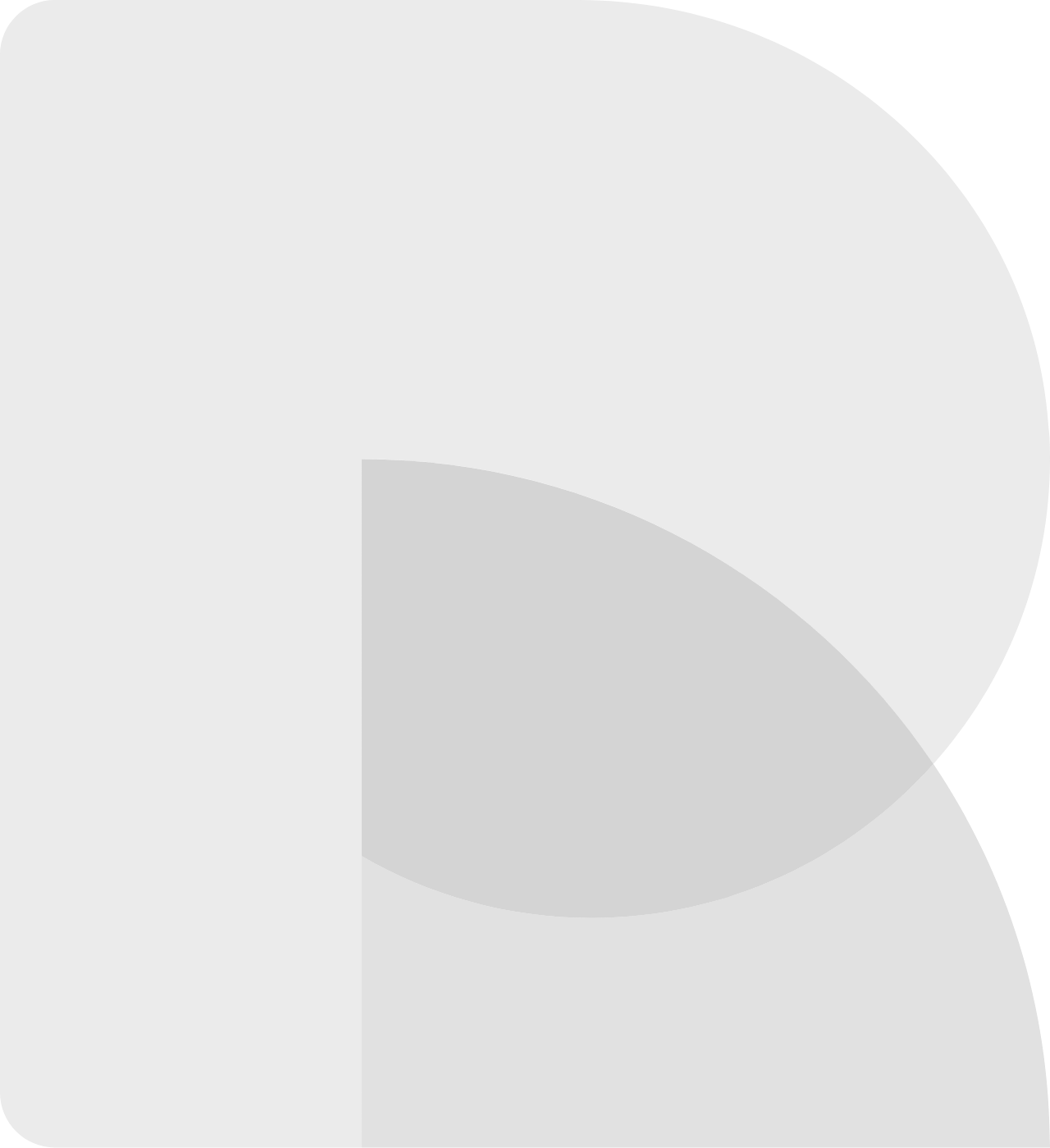
石川康晴さん 尖った民の力が、まちと教育を変える—―石川康晴さんの15年

プロフィール
石川康晴(いしかわ やすはる)
1970年岡山県岡山市生まれ。
株式会社ストライプインターナショナル (創業者)
イシカワホールディングス株式会社 (代表取締役社長)
株式会社Merci (代表取締役会長)
株式会社Waistline Group (代表取締役会長)
株式会社茶下山 (代表取締役社長)
tetta株式会社 (取締役会長)
公益財団法人石川文化振興財団 (理事長)
23歳で起業し、アパレル業界の常識に挑んできた石川康晴さん。現在は、アートで子どもの想像力を育む教育や、岡山のまちづくりに力を注いでいます。
「社会課題を見つけて、解決する」——その思いは、ビジネスでもフィランソロピーでも変わりません。そんな石川さんに、お話を伺いました。
現在の活動について教えてください。
― 事業でも、財団でも、「社会課題を見つけて解決する」
23歳で起業し、経営者歴は32年になります。企業のCEOでも、財団のプレジデントであっても一貫してきたのは、「社会課題を見つけて解決する」という姿勢です。
僕が創業したストライプインターナショナルでは、立ち上げた当初から、正社員比率や女性管理職の低さなど、業界の課題に正面から向き合ってきました。
一般的にアパレル業界では、正社員比率は約25%と低く、小売業ということもあり離職率も40%と高めで、ノウハウが社内に蓄積されにくい構造になっています。見た目を重視し、年齢を重ねた社員には自然に辞めてもらうような文化もありました。
この会社は、最終的に売上1400億円を超え、女性管理職比率は52%に。アパレル業界では珍しく、創業から15年は正社員比率100%を貫きました。
今は、公益財団法人石川文化振興財団を通じて、子ども向けの教育プログラムに力を入れています。大切にしているのは、「探求心・想像力・プレゼン力」を育てること。AIと共生していく時代、AIにはできない想像力をどう養うかがカギです。財団が運営する現代美術館「ラビットホール」は、美術を通して子どもたちに“人間らしい力”を届けるラボのような場所。18歳以下は無料で、対話型鑑賞やワークショップなどを定期的に実施しています。
また、フィランソロピーの一環として、岡山市のブランディングや地域創生にも取り組んでいます。僕自身もかなりの私財を投じています。行政主体だとどうしても弱者寄りの選択になりがちですが、世界と競える都市になるには、民間がリスクをとって“尖った”ことをやる必要がある。民が主導して渦をつくり、そこに行政が後から乗ってくる。そんな長期的視点で、30年かけて世界に開かれた街をつくろうとしています。
インバウンドを活かした観光産業の発展には、地域ごとのユニークな取り組みが不可欠です。そこに世界の富裕層が訪れ、地域経済が発展する。一方で、私たちは次世代にどんなギフトを残せるかも問われています。世界と触れるきっかけや、想像力を育む教育こそが、その答えだと信じています。単なる支援ではなく、教育という形で子どもたちに力を渡したい──そんな思いで、今も活動を続けています。
子どもの教育に関心が向かったきっかけは何ですか?
― この国の未来は子どもの未来だから。
子どもの教育に関心を持つようになった理由は大きく2つあります。一つは、高齢の方々に何を言っても、なかなか考えが変わらないという現実があること。もう一つは、単純に「この国の未来は子どもの未来」だと考えているからです。
柔軟な思考を持つ子どもたちが、私たちの財団の活動や芸術祭、地域創生に参加することで、「岡山で育ってよかった」「学べてよかった」と思えるようなシビックプライドが生まれるのではないか——そんな仮説を持っています。
ただ、子どもたちに岡山に留まってほしいというわけではありません。むしろ東京や海外に出て、しっかり学び、活躍してほしい。そして10年、20年後にUターンやIターンで岡山に戻ってきて、起業したり、家業を継いで新しい価値を生み出してくれることが、地域にとって本当に大事だと考えています。それが、僕が子どもにフォーカスしている理由です。
もともと、社会とのつながりを考えて活動されてきたのですか?
― 「自分のため」から「人のため」へ。フェーズごとに変わってきました
自分はこれまで、置かれたフェーズによって変わってきたと思っています。
起業した23歳から27歳くらいまでは、「天と地を見た」フェーズでした。起業家1年目の月給は1万円で、一日300円で生活。「人のために何かしたい」なんて余裕はまったくありませんでした。2年目で月給15万円、3年目で60万円になったものの、4年目には会社が倒産しかけて、また給料ゼロ。まさにアップダウンの連続でした。
でも、次のフェーズに入って、赤字からの翌年に利益が6億円ほど出始め、月給も100万円くらいになった頃から、少しずつ「社会のためにできることを」と考えるようになってきました。自分の生活が最低限成り立って初めて、人のため、地域のためという視点が持てたというのが正直なところです。
最初の10年は「自分のため、会社のため」。でも、10年を超えた頃から少しずつバランスが変わり始め、20年目以降は「人のため、地域のため」に軸足がどんどん移っていきました。今では、気持ちの7割以上が社会貢献に向いている感覚です。
もう、自分や会社のためにそこまで欲張る必要はない。家族に最低限のものを残せて、仲間と豊かに関われれば十分。それ以外は、人や地域のために使っていく。それが今、自分が立っているフェーズです。
フィランソロピーの現場で感じる課題を教えてください。
― 高い相続税・ねたみひがみ文化・バランスの悪い議会
社会のために活動する中で、いくつか大きなハードルを感じています。
一つは、相続税の問題です。日本では3世代も相続すれば、資産はほとんどゼロになります。海外に拠点を移したくなる人の気持ちも、正直わかるなと思います。
もう一つの課題は、地域創生を進めるうえでの「ねたみ・ひがみ」文化です。本来なら良いことをした人は称賛されるべきなのに、そうではなく、足を引っ張られる。これはかなり根深い問題で、こうした環境の中で活動を続けられる起業家がどれだけいるのか、不安になることもあります。
さらに、議員や首長の多くが、アントレプレナーの目線とまったく合わない。価値観の差が大きすぎて、地域を本気で変えていこうとすると、思いのすれ違いが起きてしまいます。
この状況を変えるには、県庁や市役所に国家試験組だけでなく、グローバルな視点を持つ中途人材を2〜3割入れていく必要があるでしょう。また、議会も多様性を持たせるべきです。女性が1/3、40歳以下が1/3、そして残りの1/3には経験豊富で本当に英知ある60〜70代のリーダーたちがいる。そんなバランスの取れた構成が理想だと思っています。
地域創生について。これまでの15年の活動で変化は感じていますか?
― 地域創生の「風」が変わった
コレクターとして活動を始めて15年、財団を立ち上げて11年が経ちました。地域創生に取り組み始めた頃は、反対の声ばかりでした。でも今、岡山市議会の全54人が僕の話を聞きたいと講演を依頼してくれた。これは大きな変化だと感じています。
起業家としてのビジネスは一足飛びでスピードが命ですが、地域創生は全く別の時間軸。30年くらいかけてじっくり進めるものと考えます。10年を越えたあたりからようやく逆風が止み、最近では少しずつ追い風を感じるようになりました。
この変化の速度は、世界共通かもしれません。ただ、早く進む地域には共通点があって、それは「首長が民間と組む覚悟を持っている」こと。その場合は、地域は倍速で変わっていきます。
ただし、起業家がそのまま首長になればいいという話ではありません。起業家は直感とクリエイティビティ、首長はデータと情報の分析。求められる能力は違います。でも、ゼロから一を生み出す起業家は、最初は理解されなくても、5年後に「あの人が言ってた世界になっている」と言われるんです。
これからどういうことをしていきますか?
― 「I am」から「We are」へ。100人のリーダーと100社をつくる。

これまでの僕の経営は、ある意味ワンマンでした。ストライプインターナショナルを23歳で立ち上げて、27年間で売上1400億円の会社に育ててきた。「ついてこい!」という形で、自分のビジョンを周囲に実現してもらう、「I am」の経営だったと思っています。
でも、これから目指すのは「We are」。たくさんの面白いリーダーたちと一緒にプラットフォームをつくっていきたい。次の四半世紀で掲げている構想は、「100人のリーダーと100社をつくり、合計で1兆円を目指す」というもの。1社あたり100億円規模の企業が生まれるような仕組みをつくり、そのうちの1%を地域にしっかり還元する。そんなエコシステムを築いていきたいと考えています。
地域創生については、これまで15年取り組んできましたが、ここからの15年は“仕上げ”の期間。4月に開館した現代美術館「ラビットホール」のアネックス(分館)を、今後15年かけて街に20か所つくっていく構想も進めています。アートと地域、経済と人の心をつなげる活動を、仲間と共に育てていきたいと思っています。
インタビュアー:Co-CEO 藤田淑子
TOP